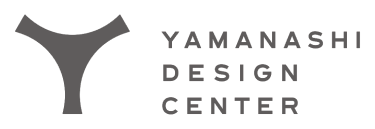News
08/キャップクラウド株式会社 上田和弥「デザイナー&クリエイターズネットワーク」登壇者の紹介
2025年04月24日
デザイナー&クリエイターズネットワーク登壇者の紹介です。
今回はキャップクラウド株式会社の上田 和弥さんです。
(登壇日:2025年4月24日)

上田 和弥
キャップクラウド株式会社
・クラウドソリューション事業
・地域創生事業
1.地域デザイン×IT
デザイン会社やクリエイターの皆さんも多いと思うのですが、私たちキャップクラウドは、実はそのような会社ではないということを先にお伝えしておきます。
先ほど私達、デザイン会社でもクリエイターの会社でもないんですよとお伝えしましたが、弊社キャップクラウドは、実はIT会社です。
本社は新宿にありまして、中小企業向けのクラウドソリューションという形で、勤怠管理や事務作業をITでサポートするような事業を展開しています。富士吉田の方では、地域創生という観点から主にコワーキングスペースの運営、宿泊、飲食、物販、観光の事業展開をしています。
一見、デザインにあまり関係していないと思われるかもしれませんが、その中で私たちが取り組んでいるのは、地域のデザインをどのように作っていくのか。そういったことを地域創生事業の中で展開をさせていただいています。
今、世の中では働き方が多様化して、「会社に出勤」してお仕事をされる方も「在宅」でされる方もいらっしゃると思います。そこで私たちは、働き方の選択肢を増やし、自分の力がどこでも発揮できるような、「自分らしい働き方」を選択できる社会を作ることを目的に「働き方、パーソナライズ」と呼んで、理念に掲げています。
2.いつでも、どこでもを目指して

2018年から、ドットワークプロジェクトの中で富士吉田市にサテライトオフィスとしての拠点を置きました。2022年からは、「富士吉田市まるごとサテライトオフィス」として、富士吉田市と包括連携協定を結ばせていただいて3年間、一緒に協働する形で動いております。
2023年には、人材育成にも力を入れて、IT人材を育てる、「.WORK+Lab(ドットワークプラスラボ)」というパソコンのルームを作っております。
少し話は変わりますが、富士吉田市内にはワークススペースとして提携している施設が40施設ありまして、どの施設にも「anyplace」というものを導入しています。
「anyplace」とは、ITの部門の事業で設計をしている、「ビーコン(Beacon)」を置くだけで、そこがコワーキングになるサービスです。それをホテルや富士急ハイランド内にあるカフェや、「FUUTO(フート)」というカフェなどの施設に設置することで、街中でも作業ができるシステムを創り、サービスとして提供しています。
40箇所の施設の中には、「高機能コワーキングスペース」が3箇所あり、ここはスタッフが常駐しているので、プリンターが使える機能などを持っている施設になります。
2023年からは、宿泊や飲食、物品事業も展開させていただいているのですが、なぜこの事業に取り組んでいるかというと、「富士吉田市の空き家問題」が大きく関わっています。
富士吉田の空き家をどんな風に、どういう形で使うか、例えば、宿泊施設として活用して、宿泊者が増え、宿泊場所としての利点が増えれば、滞在する時間も増えますし、食事できる場所があれば、そこで食事もしていただける、そういった一貫した地域滞在の向上のために今拠点を増やしております。
飲食についても、ただレストランを経営するのではなく、県内で採れる食材を地産地消で提供しています。また、冒頭にもお伝えしましたが我々はIT会社でもあるので、ITの力も取り入れて、地域の食材とITをかけ合わせ、そして更に一流のシェフとのコラボといった3つをかけ合わせた「富士山スローフード」を提供しております。

これまで私たちがどんなことを取り組んできたのかをご紹介させていただきますと、地域課題の解決や、地域の事業者さんのプロモーションを設計、また「地域内の課題は何か。」について大手のマーケターさんたちと連携してディスカッションの開催をさせていただきました。
また、地域の観光とDXをどう取り扱っていくかを議論したり、IT人材育成では、地域の方でITやパソコンのことを知らない方に向けて、無料で「みんなのIT教室」というイベントを開催させていただきました。また、コミュニティーの形成については、地域内外の方をどうコネクションさせて、地域を盛り上げていくのかといった活動をしています。
3.これからの歩み

私たちの役割の1つには、人の集まる場所として、拠点を作っているというのが大きくあります。ただ、それを作るだけでは意味がなく、作ってそこの中の人たちが、「どうやって交流するか、そしてそこをさらに町に引き込む。」ことを、我々の拠点の中でさせていただいています。
さらに、町の人にとっては何か成長する場所として、次のステップに進めるような機会を提供させていただいています。観光やアクティビティーにおいてはどんな風に周辺の地域を回ってもらうかを提案させていただいています。具体的な例をアクティビティーで挙げると、日本とイタリアをどのように繋げるのかといった事業を進めています。
日本人は文化や歴史に興味がある方が多く、イタリアも似ている部分があって、歴史的に見るとアート、芸術の街であり、食や文化に熱い街なので、そういったところで、イタリア人とコネクションを持って、一緒に地域の中でどういったコンテンツができるか、どんなものが創り出せるのかを設計している段階になります。
キャップクラウド 中村 琢哉さん:
活動を何年か行ってきている中で、見えてきたものがありまして、町の方々は、地域外の人を受入れることにすごく慣れていている方が多いです。さらに国籍や職種を問わない方々が、我々のコワーキングスペースにもいらっしゃって、なかなかそういうコワーキングスペースが地方にはないかな、というふうに思います。
今後コミュニティー形成していくにあたっては、欠かせないものとして、帰属意識と社会性と経済性の両立があると思っています。
私は2拠点生活をしているのですが、ある時私が家を出るときに、「俺、富士吉田に帰るわ」って言ったみたいで、奥さんに『あなた、帰るって北杜市に帰ってくるんじゃないの。富士吉田に行く時は「行ってくる」っていうんじゃないの。』って言われたんです。
この実体験から、こんなコミュニティーを今後、作っていく必要があることとコミュニティー作るときには社会性と経済性を両立させなければ、継続性には繋がらないと感じています。
先ほど、イタリアとの接点についてお話させていただいたのですが、これは経済的な側面についてで、社会的な側面に関しては「株式会社SAGOJO(サゴジョー)」さんと組んで今後、ファンコミュニティーを構築していきたいと考えています。
そこに参加される方々は地元の住民の方もデジタルノマドの方々も、性別も国籍も問わないで、SAGOJOさんの方でNFTを活用した「デジタル住民票」を開発していただいて、日本国内問わず販売していく中で、インバウンドの方々、それから我々と一緒になって、富士山エリアの価値を向上していくような取り組みをしていきたいと思っています。これにより、その地域に属している、コミュニティーに属しているという帰属意識が高まるのではないかと考えています。
我々は営利企業なので営利活動をやっていかないといけない中で、飲食でコラボレーションをし、インターナショナルなコミュニティー形成のために、イタリアの方々を呼び込み、観光客としてだけではなく、コミュニティー形成に継続的に興味を持っていただける方に、デジタル住民票を販売することで、キャッシュポイントを生み出したいと考えています。その中で富士吉田、河口湖で起きているオーバーツーリズムの問題も一緒に解決していきたいです。
最終的に目指したいのは、コミュニティーに属する人たちが、その一員であるという意識を持ちながら、そこの地域に対して、何かしらの貢献をする、積極的に関わっていくことを、ワールドワイドに作り上げていきたいと考えているところです。