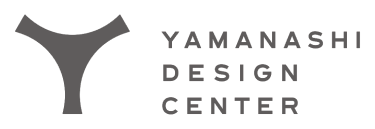News
09/MHaudio(エムエイチオーディオ) 星野 まさる「デザイナー&クリエイターズネットワーク」登壇者の紹介
2025年05月28日
デザイナー&クリエイターズネットワーク登壇者の紹介です。
今回はMHaudioの星野 まさるさんです。
(登壇日:2025年5月28日)
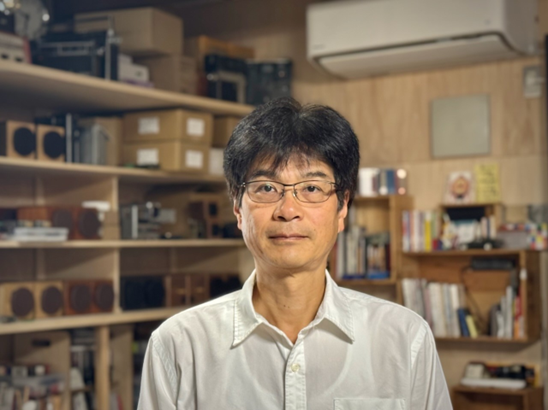
星野 まさる
MHaudio
・オーディオ機器メーカー
1.「自分のため」から始まる事業
こんにちは。星野と申します。
私は「MHaudio(エムエイチオーディオ)」という小さなオーディオ機器を作っています。
長野県の南信にある飯田の出身です。名前は「勝つ」という字なのですが、商売する上で勝ち気は良くないと思い、名刺にはひらがなで「まさる」と書いています。静岡大学の工学部機械工学科を卒業し、セイコーエプソンというプリンターを作っている会社に入社し、インクジェットプリンターの企画開発を行っていました。
2007年に、富士見町に移住しまして、妻の祖父母が住んでいた築130年の家が空き家になっていたので、そこに引っ越しました。引っ越しをした年に自分用にスピーカーやアンプを作りました。その時点では、自分用に作っていたので、売るつもりは全くなく、MHaudioという名前をつけていました。
当時、SNSはまだなかったのですが、ブログに載せていたところ、「販売してもらえないか」という問い合わせが来るようになり、少しずつ作るようになりました。2013年に、早期退職し、個人事業主として活動を始めました。

商品については、ヘッドホンアンプとスピーカーが1モデル、アンプが2モデル。
創業当時から、今も販売している商品です。
創業当初からの商品が今もメインで、モデルチェンジの必要がない。つまり、それがベストだから。
通常のメーカーはモデルチェンジを繰り返して、今年のものが良いですから、是非買ってください、とビジネスをしていくのですが、私の場合はベストなものをずっと長く使ってもらえます。
なぜなら自分用に作ったっていうのが原点だから。
買い換えないといけないというのは、おかしな話なので、そういうやり方でやっています。
2.趣味と仕事の関係値
よく「趣味が仕事になっていいね」と言われるのですが、きっかけとしては確かに趣味でしたし、「ものをいじる」ことが僕の趣味だと思うんですけど、仕事となると同じものを繰り返し作らないといけない。
個人的に言うと、趣味だったら、同じものを2つ作ることすら嫌なので、「趣味が仕事でいいね」と聞かれれば、「そうですね」と答えますが、実は「そんなことはないよ」と思っています。
趣味は自己満足の世界で、商売はお客様満足の世界なので、出発点としては趣味が商売になったというのはありますが、人に買ってもらう限り趣味にはならないです。
また商売としては、当たり前の話ですが、市販品とか同業者と競争しなければならないですし、お客さんに対する責任もあります。そして、製品としては長期的な価値が必要だし、既存ユーザーさんにとってもブランドの維持と価値を高めることが必要です。

要するに、お客さんからしたら、以前に買ったけども今はもうメーカーがない、というのは悲しいので、以前よりもよく見るねとか、買ってよかったよって思ってもらえるようにしたいと考えています。
メーカーでは、より新しいもの、より安いものを作るのが一般的なのですが、僕にとっての価値とは、お客さんにとって「本当にいいものかどうか」が基準です。
現在、販売は六本木、代官山の蔦屋書店、二子玉川蔦屋家電と一部オーディオショップで取り扱ってもらっています。最近は山野楽器、三越伊勢丹の逸品会での取り扱いもあります。問い合わせによる直接販売はしますが、簡単に買えるネットショップはないです。富士見町と岡谷市は事業について深く関わっていただいている地域で、ふるさと納税の返礼品として取り扱っていただいています。
なぜ10年以上続けることができているかというと、自分が使うために製作した理由が、市販製品には自分が気に入る音質と形の製品がなかったからなんです。自分でいうのも何ですが、たまたま作ったものが本当に音が良いものだったのです。
なぜ自分が使うために作ったものがそんなに良かったかというと、非常に謎に包まれています。テロワールという話がありましたが、タイミングとしては古民家に引っ越したときと一致しています。
僕1人でほとんど作っていますが、僕もオーディオとか凝った世代なので、自分でいろんな工夫して作ってみたことは過去にあったのですが、なぜか古民家に引っ越したときに、シンプルで簡単なものでいいから作ってみようと思って作ったのが、このスピーカーとアンプだったのです。
諏訪地域はものづくりが盛んな所でして、今でも諏訪圏メッセという工業展示会が開催されると、地元で300社ぐらい集まる地域で、僕も商品の部品は地元の方に相談して作っていただいているので、自分1人でやっているとはいえ、地域の風土、それから、産業のおかげでできているな、と思います。
基本、商品の宣伝はしません。
なぜ売り込みしないかと言うと、見た目は大きくて立派なものがいい音がするという、オーディオの世界の常識から見ると、見た目がオーディオらしくないので、仮に置いていただいたとしても、聞いてもらえなかったら意味がないと考えています。
販売される方の愛情と理解も必要なので、先方からのお声掛けがあって、なおかつ試聴できる環境を整えられる店舗さんでのみ販売をしてもらっています。
ユーザーには個人ユーザーと業務ユーザーの方がいます。
それから、音楽家とか演奏家とか映像や音響のプロの方も結構います。

空間に音が良く浸透するので、カフェやレストラン、ショップなんかでも良く使ってもらっているのですが、最近多いのは整体とか鍼灸院とか、病院関係でも使っていただいています。こういうところって利用者もそうなのですが、職員さんなんかは一日中聞いているので、音が悪いと疲れちゃうことがあって、うちの場合は「音楽がとても良く聴こえるのに、全然疲れないね」と言っていただきます。
3.良い音は「素直な音」
本質にこだわると、スピーカーの本質は音が良いこと、良い音とは「素直な音」のことであって、特徴のある音ではないです。素直な音とは、原音すなわち音声情報を変えないこと、つまり何も足さない何も引かない。
特性としてはレスポンスがよく、歪みがなく、バランスがよい、これは簡単なようで難しく、理論的側面と直感的側面、細かな配慮が必要です。

スピーカーは音楽を楽しむための道具で、道具はシンプルで汎用性が高いものが良いと考えます。しかし、「もの」として存在する以上、生活空間に調和するサイズやデザイン、質感を大切にする必要があると僕は考えています。
ここまでに至る経緯としては、「ブランドごっこ」をよくやっていました。 かつて会社でも仕事のレポートに勝手にチーム名やブランド名を作ってプレゼンをしたり、いつも楽しそうに仕事していると言われましたが、本人はいたって真面目にやっていた。
「ブランドごっこ」をすると、プレゼンテーションをしやすくなる、見てもらうには、製品の作りや製品名、ブランド名の一式の体裁が必要で、体裁がしっかりすることで、説明しやすく、認識してもらいやすくなる。
「ブランドごっこ」をすると、プレゼンテーションをしやすくなる、見てもらうには、製品の作りや製品名、ブランド名の一式の体裁が必要で、体裁がしっかりすることで、説明しやすく、認識してもらいやすくなる。
ブランドという枠組みで製品を考えることで、自分のつくるものの価値やポリシーを客観的に考えることができ、製品のあるべき姿や機能、性能をブラッシュアップすることができる。あとは、販売や事業化に必要な要件を考えられる。
重複しますが、製品はオーディオ業界の常識の逆のことをやっていますし、業態もメーカーの常識の逆のことをしていて、ずっと同じものを作って、同じ物を売って、大量生産や大量消費は目指さず、ちゃんとしたものを良いと思ってくださる方に確実に届く様にしています。